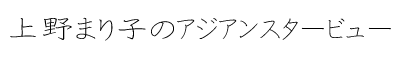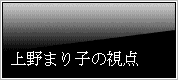鬼才キム・ギドク監督3年ぶりの作品『アリラン』3月3日〔土〕日本公開
こんにちは 上野まり子です。鬼才と言われ、世界三大映画祭を制覇した映画監督が映画界から姿を消して3年、撮影中に一人の女優が危うく命を落としそうになるという事故を機に、それまでの映画への想いと成功へと上り詰めた自身の人生について考え直すことになる。
1996年のデビューから13年で15本の作品を世に送り出し、世界を操作していると勘違いしていたと語る。その苦悩の中から、人生を映画に費やしてきて心残りはないが、映画なしでは生きていけない。映画といっしょに人生を歩いていきたいと自らの苦悩を吐露したとも言える作品、映画『アリラン』を発表した。その作品は第64回カンヌ国際映画祭<ある視点>部門最優秀作品賞を受賞した他、世界各国の映画祭に於いても高い評価を受けた。クレジットには脚本・監督、主演、製作、撮影、録音、編集、音響、美術の全てが一人の名前、その名はキム・ギドク。
先日公開となった『マイウェイ』主演のオダギリジョー、韓国女優イ・ナヨン主演で話題だった『悲夢』、事故はその撮影中に起きた。それを機にキム・ギドクは粗末な山小屋で隠遁生活することになる。共に暮らすのはただ一匹の猫、自分を見失い、泣くばかりの日々。美しくも残酷で、悲しくも甘美な映画創造の時間、自分の人生を意に介せず、無秩序に物語を描き、更に強く、更に痛みを加えて行く。それは彼の感情をも次第に蝕んで行った。
決して順調ではなかった若い時代。しかし彼は映画というジャンルで大きく羽ばたくことになった。それは世界三大映画祭のすべてでその作品が上映されるという快挙を成した。世界はキム・ギドクを自国でよりも高く評価した。輝かしいタイトルを持つ彼の元に集まっていた人々も、やがて離れていった。しかし苦悩する中でも彼は映画にこだわった。
協力者がいない中、映画を撮りたいと熱望した彼が選んだセルフドキュメンタリーという手法。自身の窮状を吐露し、苦しむキム・ギドクを揶揄し、詰問し、鼓舞するキム・ギドクは心の中のもう一人のキム・ギドク。その二人のやり取りを客観的に見つめ笑うキム・ギドク。やがてキム・ギドクの影がキム・ギドク自身に問う。「まだ何かを出来ると信じているが、その何かが本当に存在するのかも解らない」と呟くキム・ギドク。映像はやがてサスペンスを匂わすクライマックスを迎える。◆
2011年11月に開催された第12回東京フィルメックスのオープニング上映にあわせてキム・ギドク監督が来日、記者会見が行なわれた。個別インタビューを受けるべきだが、スケジュールが限れられており、共同での記者会見になった事を詫びた上、
『アリラン』が映画祭で上映される事は思ってもみなかった事で光栄だと挨拶、観客、関係者に心から感謝するとした。
東京フィルメックスでの上映のチケットは3分で完売、いかに観客が彼の復帰を待望していたかを示す形となった。Tシャツにキャップを被るスタイル多かった監督、この日は長髪に韓国伝統衣装を現代的にアレンジしたものを身に纏っていた。いつごろからその様なスタイルをしているか、ポリシーは?と問われ、気に入った一着を長く着る主義だが、これはたまたま見つけた一着で、映画のラストシーンでも着用している。今日この服にした明確な理由はないが、今着るべきはこの一着だと思ったと監督。最近は髪を伸ばし、このようなスタイルで人に会うとの事だが、良く似合うと言われるそうだ。
暮らしていた山小屋には知人のプロデューサーら3人が訪れた。その一人がオダギリジョー。“これは内緒だったんだけど!”とエピソードを紹介してくれた。実は来訪の際に、彼の事も撮影したそうだが、この作品は自分だけが出演するという位置付けだったために編集上使わないことにした。他の作品でお目にかけるチャンスがあればと含みを持たせた。
沈黙の期間で悟った事、改めて気付いた事は?には、理論的には気付きながらも、実践できないことがあると言われるが、自分もそうだった。この度、人間に必要な最小限の生活を経験する事によって、言葉では上手く表現できないが、得た物は大きかった。自分が悟った事は『アリラン』という作品に何らかの表現となっていると思うと答えた。ところで作品中で異常なまでのこだわりで自作していたエスプレッソマシーン。元々コーヒーがあまり好きではなかったという監督、では何故か。それは機械を作ること自体をしたかったから。彼は若い頃、機械工として働いていた経歴を持つ。その為撮影されたマシーン製作のシーンも、出来上がったマシーンもなかなか見事だ。因みに3年間に4台のマシーンを製作している。映画を作れない代わりにエスプレッソマシーンを作ることで自身の心を表現していたといえる。
4番目のキム・ギドクを影として登場させたのは、キム・ギドクの魂でもあり、まだ知らない自分自身を表現したもの。最後のシーンはピストルを4発撃つキム・ギドク。すべての人間は心の中に何らかの悩みを抱えているだろう。人々は他者への不満や、命、社会、国家への問題等、答えが見つからない様々な問い掛けを抱えつつ、傷つきながら生きている。様々な観念に抑圧されながら生きているが、そこから抜け出したいと想いがあった。自身を抑圧している観念の塊に3発、そして最後に観念に縛られている自分自身に1発撃ったと解説した。
(c)2011 Kim Ki-duk Film production.当初は自分自身を自身の言葉で告白しようと思い立って撮り始めたもので、作品にしようという意図はなかった。キム・ギドク1はとても苦しんでいるキム・ギドク。それを非難し、刺激するキム・ギドク2。映像の中のキム・ギドク2を登場させることにより、自身を理解しようとした。撮影しながら、ある日突然服を一枚ずつ脱ぐような感覚を覚えたという。それはまるで鬱積した気持ちが外に現れ出た感じ。怖いと思いつつ、一方では興味が湧き、考えが膨らんで行った。作品にしたのは全体の撮影量の5%、キム・ギドク1、キム・ギドク2、キム・ギドク3に加え、影キム・ギドク、殺し屋キム・ギドクが登場する事になった。次第に映画らしくなり、作品として世に出せると考え始めた。視野が広まるとテクニカルなところにも考えが及び、当初予想もしなかった方向に向かうことになった。こうしてドキュメンタリーか、ドラマか、ファンタジーかジャンルを特定できない不思議な作品となった。これまで15本の作品を撮り、2本をプロデュースして来た彼は編集でトリックを使おうとした事はない。編集は淡々と行なう作業としてあまり重要視してこなかったという。シナリオには書かれていない何かに引きつけられる感覚、何かに取り付かれたように作品に取り組むというのが、彼の変わらぬ作品制作への態度だ。振り返ってみて、これが本当に自分の作品かと思う時もあるという。ところでこの撮影は、これまでの映画用のカメラではなく、市販のデジタルカメラで行なわれた。しかも演技者も、撮影者もキム・ギドクで、思ったより複雑で工夫が必要とされた。幸い閑村の山小屋で人に見られる事もなかった。傍で見ていたら、変な人だと思われたことだろうと今は笑って話す。
健康の維持について問われた彼は、体が弱いほうだが、健康に見えたなら幸いだ。秘訣と問われれば、映画一本分のシノプシスを毎日書くことかもしれないと答えている。隠遁生活当時はそれに詩作も加わった。それらはいつの日か作品に反映することになるだろうと語る。
監督という職業はキム・ギドク監督にとって天職だと感じたという記者には、天職かは解らないが、『アリラン』を撮りながら感じた事がある。それは自身の事を自身の口で語るのは苦痛であったが、そんな時でさえ、撮影テクニックやキャラクターを考慮した事。自分が映画監督である事を改めて実感したと言う。絵を書く事も得意な監督、『アリラン』作品内にも20年前に自身が書いた作品が登場する。画家になれなかったから監督になったのかもしれないと語る。
初の映画プロモーション来日は『魚と寝る女』時、その後も多くの作品を持って来日している。3年間活動休止していたにも関わらず、以前と変わらず関心を寄せてくれた事に感謝すると語るキム・ギドク監督。日本の映画評論家の中にも引き続き評価を書き、励まして続けてくれた方がいる。日本の家族と思っている方々も来場してくれた。特に厳しい時代に物心ともに支援してくれた日本の映画関係者に感謝の辞を述べた。韓国マスコミより日本マスコミとの関係が良好と言える監督、理由を述べる事は難しいがと苦笑しつつ、多くの人々の協力があって再びこのように映画を世に出せることになった、感謝するとした。柔和な笑顔でフォトセッションに臨むキム・ギドク監督。しかし、しばしば見せる鋭い視線が鬼才と呼ばれるに相応しい貫禄も備えていた。
CGやアニメーションより、生きた人物の物語に、より興味を抱くという監督、最後に『アリラン』を発表することで扉を一つ潜り抜けた気がする。今、映画産業が大規模化し、大手配給会社を通さなければ上映さえ難しい。その状況は日本に於いても同じだろう。大手が素晴らしい作品を作り続けるのであれば問題はないが、興行成績や利益を優先することで、現在はハリウッド作品のリメイクが多いと言わざるを得ない。1990年代後半のニューウェイブ世代の監督達のような監督の誕生は難しい。韓国の中でも高い関心を呼ぶ作品や監督が少ない。行定監督からも原作のある作品が多く、オリジナル作品の製作が難しい状況だと聞く。それは韓国、日本に限らず多くの国の傾向で、その様な状況は残念でならない。映画は社会に何らかの影響を与えられるものだと今でも信じている。これまで心と精神を込めて映画製作をしてきた。世界の監督達が、その様な心を諦めずに持ち続けて欲しいと願っている。
ありがとうございましたと50分に及ぶ記者会見は終了となった。
韓国マスコミにもまだ話していない3年間の苦悩の日々、それは映画の中に表現したという監督だが話は尽きないようで、時間が許されるならば話したいことはまだまだ沢山抱えているようだ。いつの日か単独インタビュー出来る日が訪れることを願っている。
なお、『アリラン』は第12回東京フィルメックスに於いては「観客賞」を受賞している。
「アリラン」の“ア”は自我の“我”、“リ”は道理の“理”で、「自らを悟る」という一説もあるそうだ。
朝鮮民族の感情の「ハン=恨」を表現していると言われる代表的な朝鮮民謡「♪アリラン」。
歌詞の上り坂、下り坂はまさに上り下りする人生の峠を表す。さてキム・ギドクはアリラン峠を越えられたのか。
その答えはカンヌ映画祭終了後に短期間、超低予算で撮った新作『アーメン』が昨年9月にサン・セバスチャン映画祭でワールドプレミア上映されたことですでに出ているのかも知れない。また元助監督のチョン・ジェボンを監督に据えたプロデュース作品『豊山犬』も昨年6月には韓国で上映されている。
韓国映画界、いや世界映画界に復活したキム・ギドク。苦悩に立ち、それでもなお映画を撮り続けることを決心した彼の今後の作品が楽しみだ。
◆
アリラン
© 2011 Kim Ki-duk Film production.
3月3日(土)より、シアター・イメージフォーラム他全国順次ロードショー
公式サイト www.arirang-arirang.jp【作品概要】
タイトル:アリラン
原題:Arirang
2011年 韓国 91分
脚本・監督:キム・ギドク
製作:キム・ギドク
撮影:キム・ギドク
録音:キム・ギドク
編集:キム・ギドク
音響:キム・ギドク
美術:キム・ギドク
主演:キム・ギドク
(キム・ギドク1=キム・ギドク)
(キム・ギドク2=キム・ギドク)
(キム・ギドク3=キム・ギドク)
(影キム・ギドク=キム・ギドク)
(殺し屋キム・ギドク=キム・ギドク)
配給:クレストインターナショナル【今日の一言】
鬼才キム・ギドク、その名は現代の韓流ブームとは一線を画す人でも知っている有名監督だ。これまでの作品からは気難しく、少々傲慢なイメージを持っていたが、会見会場に現れた彼の姿に、それまで抱いていたイメージは最初に覆された。ゆっくりとした足取りに柔和な笑顔、丁寧な物腰。フォトセッションで見せた鋭い視線は、もう何があっても映画を諦める事は絶対にないという決心が見て取れた。
『アリラン』の試写を拝見して、物事を多面的に捉える視点を忘れえていた事に気付いた。自身でやる。そうだ、その方法があったのだと。苦境に立った時、人は何をするべきなのか。もう一度自分を振り返る機会を与えてくれる作品だと言えそうだ。
本サイトで掲載されている記事、写真の無断使用・無断複製を禁止いたします。